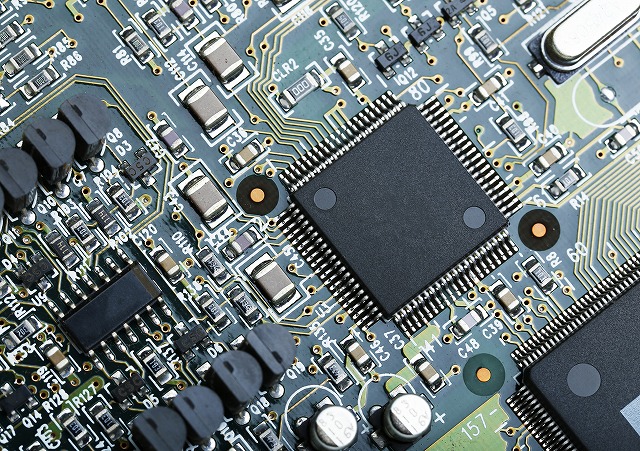CPUの購入やパソコン選びをする際にCPUコア数の目安が気になるという方は多いのではないでしょうか。CPU コア数とは、コンピューターが同時に処理できる作業の数を示す指標であり、作業の快適さや処理速度に大きく関わります。用途ごとに適切なコア数を選ぶことで、無駄のない効率的なPC環境を整えることが可能です。
本記事では、ゲームプレイや動画編集、ゲーム配信の必要数について最適なCPU コア数を詳しく解説します。さらに、サーバーや機械学習の必要数といった専門的な用途にも対応した内容となっています。 また、スマホやwindows、macといったOSごとの違いにも触れています。CPU選びの参考にしてください。
今回は最強コスパCPU10選と題して、おすすめのCPUを紹介していきます。 自作PCやBTOパソコンを選ぶとき、心臓部であるCPU選びは一番の悩みどころですよね。たくさんの種類があって、どれが自分に合っているのか、性能と価格のバランスが取[…]
-
用途ごとの適切なCPUコア数がわかる
-
WindowsやMacなど環境別の確認方法がわかる
-
スマホを含むデバイスごとのコア数の違いが把握できる
-
2025年のおすすめCPUと性能の比較ができる
CPUコア数の目安(用途別)
-
CPU コア数とは
-
ゲームに必要なコア数
-
動画編集に適したコア数
-
ゲーム配信に必要なコア数
-
サーバーに必要なコア数
-
機械学習に適したコア数
-
スマホのコア数の目安
-
WindowsとMacのコア数差
CPU コア数とは
CPUコア数とは、コンピューターの中核となる「中央処理装置(CPU)」が同時に処理できる作業単位の数を表す指標です。簡単に言えば、コアが多いほど複数の作業を一度にこなす能力が高まります。
現代のCPUは、1つのチップに複数のコアを内蔵しており、これを「マルチコア」と呼びます。例えば、4コアのCPUであれば、最大で4つの処理を並行して行うことが可能です。これにより、ブラウザを開きながら文書を作成し、同時に音楽を再生するような動作もスムーズになります。
また、コア数に加えて「スレッド数」も性能を左右する要素のひとつです。スレッドは、1つのコアが仮想的に同時処理できる作業単位を指し、例えば4コア8スレッドのCPUであれば、理論上8つの作業を並行処理できます。
ただし、コア数が多ければ常に速いというわけではありません。使用するソフトやアプリがマルチコアに対応していない場合、その効果は限定的です。したがって、コア数は使用目的に合わせて選ぶことが重要です。
用途別に必要なコア数をまとめると以下の通りです。詳しくはこのあと紹介していきます。
| 用途 | 推奨コア数 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ゲーム | 6〜8コア | 滑らかなプレイと高速読み込み | グラボとのバランスも重要 |
| 動画編集 | 6〜12コア | 高解像度での編集とエンコード | メモリ・ストレージ速度も影響大 |
| ゲーム配信 | 8コア以上 | プレイと配信を同時に安定して処理 | 高発熱に備えた冷却対策が必要 |
| サーバー | 用途により4〜16コア以上 | 複数リクエストの同時処理・安定性重視 | 用途に応じたスペック選定が必要 |
| 機械学習 | 最低でも8コア、可能なら16コア以上 | 大規模データの高速計算・トレーニング | GPUやメモリ帯域も重要 |
| スマホ | 6〜8コア | 日常的なマルチタスク処理 |
性能とバッテリー消費のバランスが重要 |
ゲームに必要なコア数

PCゲームを快適にプレイするには、最低でも6コアのCPUを搭載することが望ましいです。最近の3Dゲームやオンラインゲームでは、CPUにかかる負荷が高く、4コアでは処理が追いつかない場面も増えてきています。
主にゲームでは、キャラクターの動き、AIの処理、マップの描画などにCPUの力が使われています。高精細なグラフィックや複雑な演算が要求されるゲームほど、コア数の多いCPUの方が安定して動作します。
例えば、「Apex Legends」や「Call of Duty」などのFPSゲームでは、最低でも6コアを推奨する開発元が多くなっています。さらに、ゲーム中にDiscordで通話をしたり、ブラウザで攻略サイトを開くといったマルチタスクを行う場合は、8コア以上あると安心です。
ただし、ゲームにおいてはCPUだけでなくGPU(グラフィックボード)も非常に重要な役割を担います。CPUのコア数を増やすだけでは快適なプレイ環境は得られません。バランスの良いパーツ構成を意識することが大切です。
動画編集に適したコア数

動画編集をスムーズに行うためには、少なくとも6コア、理想的には8コア以上のCPUが必要です。編集作業では、映像のカット、エフェクトの追加、レンダリングなど多くの処理が同時に発生するため、CPUの並列処理能力が大きく影響します。
特に、4K動画や長時間の映像を扱う場合は処理量が膨大になるため、コア数の少ないCPUでは動作が重くなったり、書き出しに長時間かかることがあります。8コア以上のCPUであれば、プレビューの再生も滑らかになり、作業効率が大幅に向上します。
例えば、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveなどのプロ向け編集ソフトは、マルチコアにしっかり対応しています。6コアと8コアで比較すると、エンコード速度やリアルタイム編集の快適さに体感できる違いがあるでしょう。
ただし、コア数ばかりに注目してしまうのは危険です。編集作業ではメモリ容量やストレージ速度、GPU性能も影響します。これらを総合的に整えることで、初めて快適な動画編集環境が整います。
ゲーム配信に必要なコア数

ゲーム配信には8コア以上のCPUが推奨されます。というのも、ゲームプレイと配信ソフトの同時実行はCPUに大きな負荷をかけるためです。
ゲームだけを快適に動かすには6コアあれば十分な場合もありますが、そこに配信処理が加わると、処理能力が不足しやすくなります。OBS Studioなどの配信ソフトは、リアルタイムで映像をエンコードしながら送信するため、CPUのリソースを大きく消費します。
例えば、ApexやFortniteのようなグラフィックが重めのゲームを高画質で配信する場合、8コア16スレッド以上のCPUでないとフレームレートが安定しないことがあります。配信画面のカクつきや音声の遅延が発生しやすくなるため注意が必要です。
もちろん、配信の解像度やフレームレート設定によって必要なコア数は変わってきます。軽量設定であれば6コアでも可能ですが、安定性を重視するなら8コア以上を選ぶとよいでしょう。
サーバーに必要なコア数
用途によって異なりますが、サーバーに求められるCPUコア数は最低4コア、多くの場合8コア以上が望まれます。特に同時アクセスが多いWebサーバーや、データベース処理を行うバックエンドサーバーでは処理能力の高さが求められます。
例えば、社内のファイル共有程度の軽量な用途であれば4コアでも運用できますが、クラウド上でのアプリケーション提供や仮想マシンの運用となると、8~16コア程度のCPUが安定した処理に役立ちます。
また、同時接続数が多いと、リクエスト処理が遅延しやすくなるため、コア数が不足するとレスポンスが悪くなります。業務用サーバーやゲームサーバーでは、コア数とスレッド数の両方を重視するのが基本です。
ただし、サーバーにおいてはCPUだけでなく、メモリ容量やネットワーク帯域、ディスク速度もボトルネックになりがちです。CPU性能だけで判断せず、全体の構成を考えることが安定運用のポイントです。
機械学習に適したコア数

機械学習を行うPCでは、最低でも8コア以上、できれば12コア以上のCPUが理想的です。機械学習では、大量のデータを何度も計算・解析するため、並列処理に優れたCPU構成が求められます。
例えば、Pythonで構築された学習モデルを繰り返し実行する場合、各工程でCPUの演算能力がパフォーマンスに直結します。特に、CPUベースで学習を回すような環境では、コア数が多いほど処理時間を短縮できます。
ただし、多くの機械学習フレームワーク(TensorFlowやPyTorchなど)は、GPU処理に最適化されています。そのため、高速なGPUを搭載する場合は、極端に多いコア数がなくてもパフォーマンスを確保できます。あくまで補助的な役割としてCPUの並列処理性能を考慮しましょう。
このように、CPUだけに依存せず、GPUとのバランスを取った構成が、効率よく学習を進めるためのポイントになります。コストとの兼ね合いも考慮しながら、必要に応じて12コア・16コアといった上位モデルを検討するのも有効です。
スマホのコア数の目安
スマートフォンにおいては、6コアまたは8コアが一般的な目安となります。これは、スマホでもアプリの同時実行や高画質動画の視聴など、ある程度の処理性能が求められるためです。
例えば、SNSを見ながら音楽を流す、カメラを使いながら地図アプリを開くといったマルチタスクでは、複数のコアが同時に稼働することで動作がスムーズになります。4コアの端末でも動作は可能ですが、複数アプリを立ち上げると動きが鈍くなることがあります。
また、最近のスマホでは「高性能コア+省電力コア」を組み合わせた設計が主流です。これは、処理の重いアプリでは高性能コアが働き、待機中や軽い処理では省電力コアが活躍する仕組みです。そのため、単純にコア数が多い=高性能とは限りません。
普段使いであれば6コア程度でも十分ですが、ゲームや動画編集アプリを快適に使いたい方は、8コア以上を選ぶとより安心です。バッテリー消費も影響するので、性能と省エネのバランスを見て選ぶことがポイントです。
WindowsとMacのコア数差
WindowsとMacの間におけるコア数の違いは、OSそのものではなく搭載されているCPUの種類によって生じます。つまり、「OSによる性能差」ではなく、「採用されているハードウェアの傾向」による違いです。
MacはAppleシリコン(M1やM2)を搭載して以降、標準で8コア以上を持つモデルが中心となりました。特にM1 ProやM2 Maxでは、最大12コアを超える構成も用意されており、画像処理や動画編集において高い処理性能を発揮します。
一方、Windowsパソコンは搭載されるCPUの選択肢が非常に広く、エントリーモデルでは4コアのCPUも多く見られます。ただし、ゲーミングPCやワークステーション向けでは、12コアや16コアのハイエンドモデルも選択可能です。
そのため、コア数だけを見ればMacの方が高性能に見えることもありますが、Windowsはニーズに応じて多彩な構成が選べるという柔軟性があります。高性能を重視するならどちらも選択肢となり得ますが、コスパや拡張性を考慮する場合は、Windowsの方が自由度が高いといえるでしょう。
CPU コア数の確認方法(環境別)
-
Windowsのコア数の確認方法
-
Macのコア数の確認方法
-
Linuxのコア数の確認方法
-
iPhone
-
Android
-
2025おすすめCPUと性能比較
Windows

Windowsでは、タスクマネージャーを使えば簡単にCPUのコア数を確認できます。
まず、画面下のタスクバーを右クリックして「タスクマネージャー」を選びましょう。表示されたウィンドウで「パフォーマンス」タブをクリックし、「CPU」を選択すると、右下に「コア数」と「論理プロセッサ(スレッド数)」が表示されます。
この方法であれば、特別なソフトを入れることなく、現在使用しているCPUの基本的な構成を把握できます。ただし、表示されるのは物理コアと論理スレッド数で、CPUの世代や種類は別途「システムの詳細情報」から確認する必要があります。
Mac
MacでCPUのコア数を確認するには、「このMacについて」から確認するのが最も手軽です。
まず画面左上のAppleマークをクリックし、「このMacについて」を選択します。次に表示されるウィンドウで「詳しい情報」をクリックすると、使用中のMacのプロセッサ情報が確認できます。
また、より詳しく知りたい場合は、「アクティビティモニタ」アプリを使う方法もあります。ユーティリティフォルダ内にあるこのツールを起動し、「ウィンドウ」メニューから「CPU使用率」を選ぶことで、リアルタイムの負荷状況やスレッド数なども把握可能です。
ただし、プロセッサの名称からコア数を逆算する必要がある場合もあるため、Apple公式サイトで該当モデルの仕様を調べるのも有効です。
Linux
Linuxでは、ターミナルを使ってコア数を確認できます。
もっとも基本的な方法は、次のコマンドを入力することです。
lscpuこのコマンドを実行すると、CPUアーキテクチャ、物理コア数、スレッド数、モデル名など、詳細な情報が表示されます。
「CPU(s):」の行に書かれているのが論理プロセッサ数、「Core(s) per socket:」が物理コア数です。
もう一つの方法として、次のようなコマンドもあります。
cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores"この方法はやや詳細に踏み込んだ情報取得に向いており、複数CPU構成のサーバーなどでも有効です。
ただし、ディストリビューションやカーネルのバージョンによって表示が微妙に異なるため、結果の読み取りには注意が必要です。
iPhone

iPhoneでは、設定画面から直接CPUのコア数を確認することはできません。
そのため、iPhoneのCPUコア数を調べるには、モデル名をもとにスペック情報を外部サイトで確認する必要があります。たとえば、「iPhone 14 Pro チップ構成」などと検索すれば、Apple公式サイトや信頼できる技術系メディアで正確な情報が見つかります。
多くの最新iPhoneは、Apple独自のAシリーズまたはMシリーズのチップを搭載しており、6コアまたは8コア構成が主流です。
たとえば、A16 Bionicチップは2つの高性能コアと4つの高効率コアからなる6コア設計です。
一般的な使い方では、こうした詳細を知らなくても支障はありませんが、アプリ開発や検証用途で正確なCPU情報が必要な場合には、無料の情報アプリ(例:Lirum Info Liteなど)を使うのが便利です。
Android
Androidでは、無料のアプリを使えばCPUのコア数を簡単に確認できます。
たとえば、「CPU-Z」や「Device Info HW」などのアプリをインストールすると、CPUの型番、動作周波数、コア数といった詳細な情報が一覧で表示されます。
Androidスマートフォンはモデルによって搭載されているCPUが異なり、2コアから最大16コアまで幅広い構成があります。
特にハイエンド機種では、複数の高性能コアと省電力コアを組み合わせた「ビッグリトル構成」が採用されており、効率よく処理を行えるよう設計されています。
ただし、コア数が多ければ必ずしも体感速度が上がるわけではありません。ソフトウェアの最適化や搭載メモリ、OSバージョンなどもパフォーマンスに影響するため、総合的な視点で性能を判断することが大切です。
2025おすすめCPUと性能比較
2025年の最新CPUは、性能や価格のバランスがさらに洗練されており、用途別に最適なモデルを選ぶことが重要です。ここでは、利用目的ごとにおすすめのCPUを紹介し、それぞれのスペックや価格帯も比較できるように表にまとめます。
用途別おすすめCPU一覧(2025年版)
| 用途 | おすすめCPU | コア数 / スレッド数 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|---|
| 軽作業(文書作成・Web) | Intel Core i3-13100 | 4コア / 8スレッド | 低価格で十分な性能、低消費電力 |
| AMD Ryzen 3 5300G | 4コア / 8スレッド | グラフィック機能内蔵、省スペースPCにも最適 | |
| ゲーム・動画視聴 | Intel Core i5-13500 | 14コア / 20スレッド | 高い処理能力とコスパ、多くのゲームで快適動作 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 6コア / 12スレッド | ゲーム・編集の両方で安定、最新世代で効率良好 | |
| 動画編集・ゲーム配信 | Intel Core i7-14700K | 20コア / 28スレッド | 高解像度編集もスムーズ、ストリーミングにも対応 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 8コア / 16スレッド | ゲーム特化型、L3キャッシュが大容量で描画が滑らか | |
| 機械学習・3DCG制作 | Intel Core i9-13900K | 24コア / 32スレッド | 最大級の処理能力、大規模計算も安定 |
| AMD Ryzen 9 7900 | 12コア / 24スレッド | 処理能力とコストのバランスが良く、多用途で活躍 |
CPUを選ぶ際のチェックポイント
-
予算とのバランスを見る
-
「高性能=ベスト」ではありません。使わない性能にお金を払うのは非効率です。
-
-
対応ソケットを確認する
-
Intelなら「LGA1700」、AMDなら「Socket AM5」など、マザーボードとの互換性に注意。
-
-
TDP(熱設計電力)も重要
-
高性能なCPUほど発熱量も多くなります。冷却対策も視野に入れて選ぶ必要があります。
-
どれを選ぶか迷ったときは
次のような考え方で絞り込みましょう。
-
汎用性・価格のバランスを求めるなら → Core i5-13500
-
編集や配信をよく行うなら → Ryzen 7 7800X3D
-
高性能を最優先するなら → Core i9-13900K
多くの選択肢がありますが、「何を重視するか」で最適なCPUは大きく変わります。この一覧を参考にしながら、次の見出しで紹介する「作業別コア数の目安」や「CPU確認方法」と組み合わせて、自分にぴったりのモデルを見つけてください。ご自身の使い方に合ったCPUを選ぶことで、無駄なく快適なPC環境が整えられます。
CPU コア数 目安の総まとめ
-
CPUコア数は同時処理能力を示す指標
-
ゲームには6〜8コア程度が快適な基準
-
動画編集には8コア以上あると作業がスムーズ
-
ゲーム配信には8コア以上が安定動作に適する
-
サーバー用途は処理内容に応じて4〜16コアを使い分ける
-
機械学習では12コア以上が効率的に学習を進めやすい
-
スマホは6〜8コアでマルチタスクと省電力のバランスが取れる
-
Macは標準で8コア以上のAppleシリコンを搭載する傾向がある
-
Windowsは用途に応じて2〜16コアまで選択肢が広い
-
Windowsではタスクマネージャーで簡単にコア数が確認できる
-
Macでは「このMacについて」からプロセッサ情報を確認できる
-
Linuxはターミナルで「lscpu」コマンドを使って把握できる
-
iPhoneは外部サイトやスペックアプリでコア構成を確認する
-
Androidは「CPU-Z」などの無料アプリで確認可能
-
2025年のおすすめCPUは用途別にCore i5からRyzen 9まで幅広い