パソコンの自作やアップグレードを検討している中で、ギガバイトのマザーボードの評判が気になっている方も多いのではないでしょうか。ギガバイトはどこの会社なのか、製品の特徴やシェア、そして実際に使った耐久性や修理対応、保証制度まで、気になるポイントはたくさんありますよね。
本記事では、ギガバイトのマザーボードについて一部ユーザーからの「買ってはいけない」と言われる理由や、購入前に知っておきたい注意点を含めて、分かりやすく解説していきます。初心者から経験者まで役立つ内容を、ギガバイトの評判やシェア状況、製品ごとの違いにも触れながらお届けします。
-
ギガバイトのマザーボードの主な特徴や性能
-
購入前に知っておきたいデメリットや注意点
-
他社と比較したときの保証内容やサポート体制
-
市場でのシェアや評価の立ち位置
ギガバイトのマザーボードの評判や特徴
-
ギガバイトのマザーボードの特徴は?
-
ギガバイトは買ってはいけない?
-
シェアと市場での立ち位置
-
マザーボードの耐久性は?
ギガバイトのマザーボードの特徴は?
ギガバイトのマザーボードは、コストパフォーマンスと製品ラインナップの豊富さが大きな特徴です。特に、初心者向けからハイエンドゲーマー向けまで、用途に合わせた製品が用意されている点が魅力となっています。
具体的には、「AORUS(オーラス)」シリーズのような高性能なゲーミング向けモデルから、リーズナブルでシンプルなベーシックモデルまで揃っており、選びやすいのが利点です。また、同価格帯で比較したとき、ASUSやMSIよりもやや安価なケースが多く、予算を抑えたいユーザーにとっては手が届きやすい存在と言えるでしょう。
その一方で、マニュアルやサポート情報の充実度ではやや物足りなさを感じるという声もあります。日本語での詳細な情報が少なく、BIOS(基本設定画面)のチューニングに慣れていない方にとっては、最初の設定が難しく感じるかもしれません。
つまり、ギガバイトのマザーボードは「価格重視」「スペック重視」の人には魅力的ですが、「設定やトラブル対応に不安がある」という方には少しハードルが高く感じる場面もあります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 製品ラインナップ | 初心者〜ハイエンドユーザー向けまで幅広く展開 |
| 価格帯 | 他社と比べて同スペックなら比較的リーズナブル |
| 技術的特徴(例:DualBIOS) | 一部モデルに安全性重視の機能が搭載されている |
| 日本語情報の充実度 | やや少なめで、英語情報を探す必要があることも |
ギガバイトは買ってはいけない?

「ギガバイトは買ってはいけない」と言い切ることはできませんが、注意すべき点がいくつかあるのは事実です。選ぶ際にはメリットとデメリットの両方を理解することが大切です。
まず、ギガバイト製品は価格の安さが魅力でありながらも、BIOSのアップデート対応が他社と比べて遅い傾向があります。たとえば、Intelの新しいCPUに関する更新が必要になった際、ASUSやMSIは比較的早い段階でベータ版を含めたアップデートを提供していましたが、ギガバイトは対応が後手に回っていました。
また、ギガバイト製の一部モデルには、いわゆる「パーツガチャ」と言われる仕様も存在します。これは、同じ型番の製品でも、実際に入っている部品(Wi-Fiチップなど)が異なる可能性があるという点です。開封するまでどちらのパーツが使われているかわからないため、パーツ構成にこだわる方には不向きです。
こうした点から、特に「安定性」や「サポート重視」の方にはやや不安要素があるかもしれません。ただし、製品自体がすべて悪いわけではなく、コスト重視で使いこなせるユーザーにとっては十分な選択肢です。
注意すべきポイントまとめ:
-
BIOSアップデートが遅い傾向がある
-
同型番でも構成パーツにばらつきがある(パーツガチャ)
-
日本語での技術サポートや情報量が少ない
-
初心者やサポート重視の方には不向き
シェアと市場での立ち位置
ギガバイトは、世界的に見ても有名なマザーボードメーカーであり、ASUS・ASRock・MSIと並んで「世界4大メーカー」の1社として数えられています。台湾に本社を置き、1986年から続く老舗メーカーであることも信頼性につながっています。
ただし、国内市場に限ると、ASUSが圧倒的に支持されており、価格比較サイトやレビュー投稿数を見るとその差は明らかです。その理由としては、ASUSは日本語での情報発信が多く、トラブル時の対応や技術サポートの信頼度が高い点が挙げられます。逆に、ギガバイトはそういった点でやや後れをとっており、ユーザーサポートや情報量の少なさが影響していると考えられます。
また、ユーザー層にも違いが見られます。ASUSやMSIは「初めて自作する人」や「トラブル対応が不安な人」に人気があり、ギガバイトは「ある程度経験があり、設定や調整を自分でできる人」からの支持が目立ちます。
| メーカー名 | 世界的な評価 | 日本市場での人気 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ASUS | 非常に高い | 非常に高い | 日本語サポートと安定性が強み |
| GIGABYTE | 高い | 中〜やや低め | コスパ重視、一部モデルに個体差あり |
| MSI | 高い | 高い | ゲーミング性能と安定感 |
| ASRock | 中〜高め | 中 | 価格重視派に人気 |
マザーボードの耐久性は?

マザーボードの耐久性については、多くのユーザーが気になるポイントです。ギガバイトのマザーボードは、一般的には安定性もあり、長く使える製品として評価されています。ただし、モデルやロットによって品質のばらつきがあるという指摘も一部にあります。
例えば、ギガバイトはミドルレンジ製品でもDualBIOS(2つのBIOSチップを搭載してトラブル時の復旧をサポートする機能)を採用しているなど、ハードウェア面では信頼性の高い技術も積極的に導入しています。これは設定ミスやアップデート失敗時に復旧しやすいという利点があります。
一方で、前述の通り、同一製品でも使用されている部品が異なる場合があり、これが品質にばらつきを生む原因となっています。Wi-FiチップやBluetoothモジュールがIntel製かRealtek製かで性能や安定性が微妙に違うケースも報告されています。
このように、設計や基本構造自体の耐久性は高めですが、細部のパーツによる個体差には注意が必要です。特に長期的に使う予定の人は、購入前に信頼できるレビューや検証情報を確認しておくと安心です。全体としては、正しく扱えば数年単位で使用できるだけの耐久力は十分にあるといえるでしょう。
耐久性に関するチェックポイント:
-
DualBIOSなど、リスク回避機能が搭載されたモデルがある
-
通常使用での寿命は5〜7年が目安
-
個体によって内部パーツが異なる場合があるため、事前調査が大切
-
オーバークロックや高負荷用途では冷却対策も重要
ギガバイトのマザーボードの注意点
-
保証内容と他社との違い
-
修理対応の流れと期間
-
サポート体制と対応が遅い?
-
日本語での情報量が少ない?
-
ギガバイト製品を買う際の注意点
保証内容と他社との違い
ギガバイトのマザーボードには、製品に応じた保証期間が設定されています。通常は1年から3年の保証があり、一部の高価格帯モデルには4年保証が付くこともあります。ただし、これはあくまで正規代理店からの購入であることが前提です。中古品や個人売買、保証シールのない並行輸入品などは、サポート対象外となるため注意が必要です。
他社と比較すると、保証年数やサポートの範囲は大きな差はありませんが、対応方法に若干の違いがあります。たとえばASUSやMSIは、一部の製品でユーザーが直接メーカーに問い合わせ可能なのに対し、ギガバイトは販売店を通じての修理依頼が基本となっています。
また、ギガバイトは「ピン折れ保証」などの独自サービスを一部製品に提供しています。CPUソケットのピン曲がりなどは通常保証対象外となりがちですが、購入から6ヶ月以内であれば無償修理が可能です。この点は初心者にとっても心強いポイントです。
| 項目 | GIGABYTEの保証特徴 | 他社(例:ASUS, MSI)との違い |
|---|---|---|
| 保証期間 | 1〜3年(モデルにより最大4年) | おおむね同等 |
| 保証の条件 | 正規代理店購入+保証シールが必要 | 条件は似ているが、直販での受付があることも |
| 特別保証(例:ピン折れ) | 一部製品にて6ヶ月以内の無償修理あり | 基本は保証外が多い |
| 保証受付の流れ | 購入店経由での受付が基本 | メーカー直受付も可能な場合あり |
修理対応の流れと期間
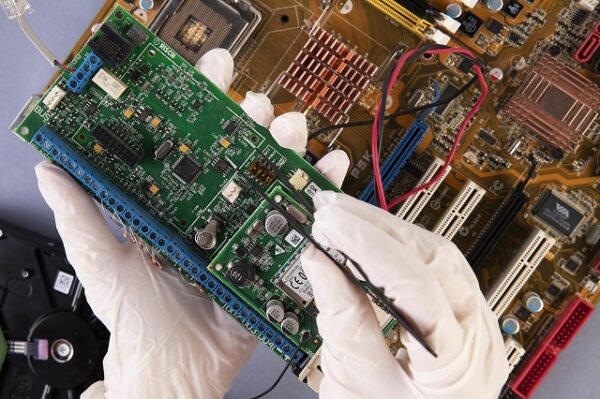
ギガバイト製マザーボードが故障した場合の修理対応は、まず購入した販売店に連絡することから始まります。ネット通販で買った場合も、基本的にはそのショップが窓口となるため、店舗ではなくメーカーに直接送ってしまわないよう注意が必要です。
実際の流れとしては、販売店からGIGABYTEの修理部門に製品が送られ、そこから修理がスタートします。この工程に入ってから、修理が完了するまでにおおよそ2〜4週間ほどかかるのが一般的です。なお、この期間中は代替品の貸し出しなどは行われていないため、PCが使えなくなる可能性もある点は覚えておいた方が良いでしょう。
修理対応の流れ(例):
-
購入した販売店に連絡
-
修理依頼用紙に必要事項を記入
-
故障品と必要書類(保証シール、購入証明など)を販売店に提出
-
販売店からGIGABYTEの修理部門へ発送
-
修理(通常2~4週間)
-
修理完了後、販売店を通じて返却
このように、修理のたびに複数のステップを踏む必要があり、スピード重視の人にはやや煩雑に感じるかもしれません。
サポート体制と対応が遅い?
ギガバイトのサポート体制に関しては、「対応が遅い」という声が一部のユーザーから聞かれます。特に問題視されがちなのが、BIOSのアップデート対応です。これは、CPUの新モデルに対応させるために必要なソフトウェアの更新ですが、GIGABYTEは他社と比べてリリースのタイミングが遅れるケースがあります。
たとえば、Intelの第13・14世代CPUに関するマイクロコード対応が発表された際、ASUSやMSIが早期にベータ版BIOSを公開していたのに対し、GIGABYTEは数週間遅れての対応となりました。これにより、特定の不具合(アイドル時の再起動やブルースクリーンなど)に悩まされたユーザーが、不満を感じたようです。
また、サポートの連絡窓口がわかりづらいという指摘もあります。電話サポートも設けられていますが、受付時間が限られており、メール返信も時間がかかることがあります。
こうした点を踏まえると、トラブル時に迅速な対応を期待する方や、最新パーツへの柔軟な対応を重視する方は、あらかじめそのリスクを理解しておくと良いでしょう。
日本語での情報量が少ない?

GIGABYTEの製品に関する情報は、英語圏では比較的多く見つかりますが、日本語での情報はかなり限られています。これは、初心者や英語が苦手なユーザーにとっては大きなハードルとなるかもしれません。
特にBIOSの設定やオーバークロック(性能を上げるための細かな調整)に関する情報を探す場合、ASUSやMSIは日本語の公式ドキュメントや解説記事が豊富にある一方で、GIGABYTEはほとんどが英語フォーラムや海外の個人ブログなどになります。
実際に、ユーザーが求めるような「この設定をこう変えれば安定する」といった具体的な情報は、英語サイトでようやく見つかるといったケースも珍しくありません。
日本語情報が少ないことで起きる困りごと:
-
BIOS設定で困ったときに検索しても日本語の解説が出てこない
-
トラブル時の解決策が海外フォーラム頼りになる
-
自作初心者がつまずきやすく、最悪PCが起動しないまま放置される
情報量の豊富さは、実は「使いやすさ」や「安心感」にも直結します。製品の性能だけでなく、こういったソフト面も選ぶポイントに含めておくと失敗を防ぎやすくなります。
ギガバイト製品を買う際の注意点
ギガバイトのマザーボードはコストパフォーマンスに優れており、うまく使いこなせば良い選択肢となります。ただし、購入前にいくつかの注意点を押さえておくことが重要です。
まず、「同じ製品名でも中身が異なる可能性がある」という点です。これは「パーツガチャ」と呼ばれ、Wi-FiやBluetoothのチップがIntel製かRealtek製かで違うなど、仕様が安定していないことがあります。どのパーツが使われているかは開封しないとわからないため、気になる人はレビューや事前情報をしっかり調べておくと安心です。
次に、サポート対応や情報面での不安が残るため、初心者が最初に選ぶマザーボードとしてはややハードルが高めかもしれません。逆に、ある程度経験があり、多少のトラブルにも自分で対応できる方にとっては、魅力的な価格とスペックを両立した製品となります。
購入前に確認しておきたいポイント:
-
正規代理店から購入する(保証対応に必要)
-
製品の仕様やリビジョン(バージョン)違いに注意
-
使いたい機能(Wi-Fiなど)が実際に搭載されているか事前に確認
-
自力で調べたり設定したりする準備があるかどうか
これらを踏まえて選べば、ギガバイト製品も十分に「アリ」な選択肢になります。
ギガバイトのマザーボードの評判のまとめ
-
製品ラインナップが幅広く初心者から上級者まで対応
-
コストパフォーマンスが高く価格を抑えやすい
-
AORUSシリーズなどゲーミング向けモデルが豊富
-
同価格帯のASUSやMSIより安価なケースが多い
-
日本語マニュアルや情報が少なく初心者にはやや不向き
-
BIOSのチューニングや設定に慣れていないと戸惑うことがある
-
BIOSアップデートの対応が他社より遅れがち
-
製品ごとにパーツ構成が異なる「パーツガチャ」が存在
-
世界4大マザーボードメーカーの一つとして評価は高い
-
国内市場ではASUSに人気で差をつけられている
-
ギガバイト製は自作経験者に支持される傾向がある
-
DualBIOSなど信頼性の高い技術も一部モデルに採用
-
保証は1〜3年が基本で一部に4年保証付き製品もある
-
保証受付は購入店舗経由での対応が基本となっている
-
日本語の技術情報が少なく英語フォーラムの利用が必要な場面がある
