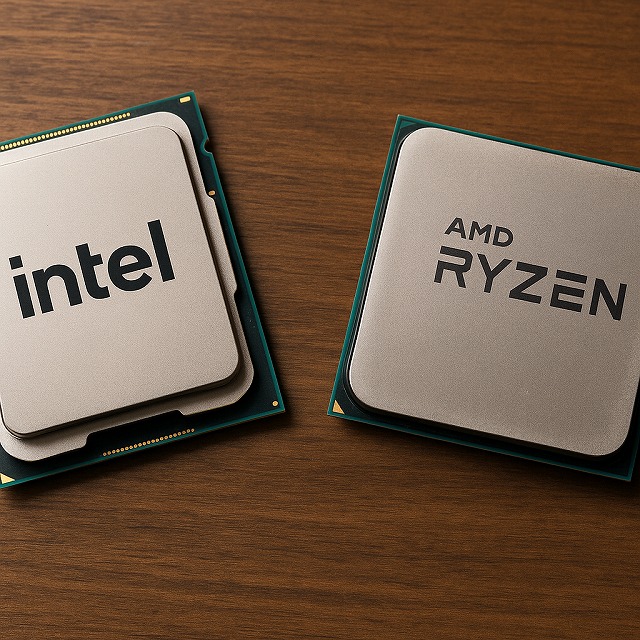パソコン選びの中でも重要なパーツであるCPU。その中心には「インテル(Intel)」と「ライゼン(Ryzen)」という2大ブランドが存在します。この記事では、CPU インテル ライゼンの違いに注目し、どっちを選ぶべきか迷っている人に向けて、比較情報をわかりやすく解説していきます。
性能や価格、世代ごとの特徴はもちろん、ベンチマークスコアや用途別の最適解(ゲーム、配信、動画編集など)についても詳しく紹介。また、インテルの不具合や、ryzen やめとけといった噂、動かないソフト一覧に関する実例も取り上げ、選ぶ前に知っておきたい注意点も網羅しています。
さらに、CPU インテル ライゼン 以外の選択肢も検討したい方向けに、Apple MシリーズやARM系CPUといった代替案も紹介します。これからパソコンを選ぶ方、買い替えを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
インテルとライゼンの性能や設計の違い
-
用途別(ゲーム・配信・編集)での最適なCPUの選び方
-
世代や価格によるコスパや性能の比較ポイント
-
インテルやライゼンに関する不具合や動作しないソフトの事例
CPU インテル(Intel)とライゼン(Ryzen)の違いを解説
-
インテルとライゼンの違いは?
-
インテルとライゼンはどっちが人気?
-
性能や世代の違いに注目
-
価格とコスパを比較
-
ベンチマークで見る性能差
インテルとライゼンの違いは?
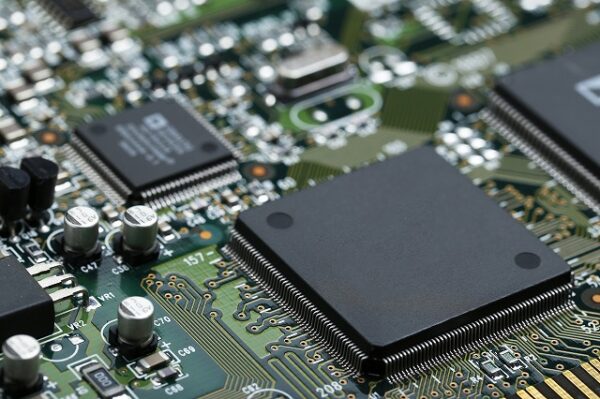
パソコンの中心的な部品であるCPUには「インテル(Intel)」と「ライゼン(Ryzen)」という2大ブランドがありますが、両者は性能や設計思想にいくつかの明確な違いがあります。それぞれの特徴を知ることで、自分の使い方に合ったCPUを選ぶことができるようになります。
まず、インテルのCPUはシングルコア性能が非常に高いことが特徴です。これは、一つの作業を素早く処理する能力に優れていることを意味しており、Web閲覧やオフィスソフトの使用、そして多くのPCゲームにおいて快適な動作を実現します。特にFPSやMOBAなど、処理速度が重要なゲームジャンルでは、インテル製CPUが安定したフレームレートを出しやすいと評価されています。
一方のライゼンは、マルチコア・マルチスレッド性能が高く、複数の作業を同時にこなす処理に向いています。たとえば、動画編集ソフトでのエンコード処理や、同時に複数のアプリを開いて作業をするマルチタスク環境では、ライゼンの方がスムーズに動作するケースが多くあります。
アーキテクチャ面でも両者は大きく異なります。インテルは第12世代以降、「Pコア(高性能コア)」と「Eコア(省電力コア)」を組み合わせたハイブリッド構成を採用しており、これにより作業内容に応じたコアの最適な割り当てが可能となりました。ライゼンは、コアの構成がすべて均一であるシンメトリックな設計を特徴とし、特にプロ向けの並列処理に強みを持っています。
以下の表で両者の違いを整理してみましょう。
| 項目 | インテル | ライゼン(AMD) |
|---|---|---|
| 強み | シングルコア性能、ゲーム性能 | マルチコア性能、マルチタスク性能 |
| アーキテクチャ | ハイブリッド(P/Eコア)設計 | 均一なコア構成、チップレット設計 |
| マザーボード互換性 | 世代ごとにソケット変更が多い | AM4/AM5で長期間の互換性を維持 |
| 内蔵グラフィック対応モデル | 多くのモデルに搭載 | G付きモデルのみ(Ryzen 5 5600Gなど) |
| 初心者向けの使いやすさ | ドライバやBIOSの安定性が高い | 自作慣れしていない場合は設定がやや複雑な場合も |
このように、両者は性能面だけでなく、設計思想や使い勝手の面でも違いがあり、自分のPC用途に合わせて適切なCPUを選ぶことが重要です。
インテルとライゼンはどっちが人気?
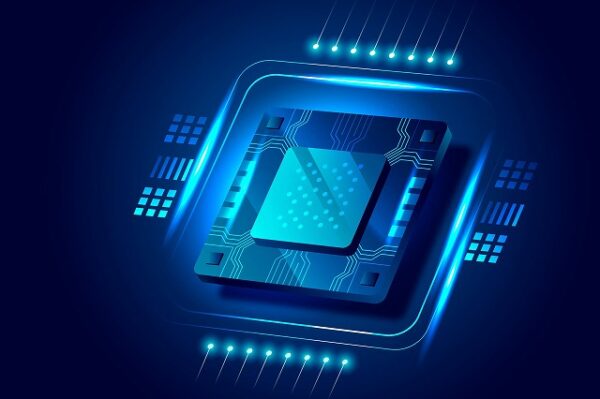
CPU選びで迷う多くのユーザーが気にするポイントのひとつが、「結局どっちが人気なのか?」という点です。結論としては、現在の市場においてはインテルがやや優勢ですが、これは使い方や用途によって評価が分かれるため、一概には言えません。
たとえば、ゲーム用途ではインテルが多く選ばれている傾向にあります。これは、前述の通り、インテルCPUのシングルスレッド性能が高いためで、1フレームの遅延が重要なFPSやアクションゲームで安定したパフォーマンスを発揮するからです。また、インテル製CPUは、ゲーム開発時にリファレンス(基準)として使われることも多いため、最適化されやすいという側面もあります。
一方で、動画編集や配信、3Dモデリングなどクリエイティブな作業を重視するユーザーからはライゼンが高く評価されています。理由はシンプルで、同価格帯でコア数が多く、並列処理に優れているため、重たいタスクをスムーズに処理できるからです。また、自作ユーザーの間では、ライゼンのチップレット設計による拡張性の高さも人気の一因です。
▼主な用途別人気傾向:
-
ゲームメイン:インテル(FPSやRTSなど)
-
動画編集・配信:ライゼン(Premiere ProやOBS使用者)
-
日常用途・ネット閲覧:インテル(安定動作)
-
コストパフォーマンス重視:ライゼン(同価格帯で高性能な傾向)
-
自作・上級者志向:ライゼン(設定の自由度とパーツの選択肢が広い)
市場全体ではインテルがややシェアを持っているものの、ライゼンは「知って選ぶユーザー」による高い支持があり、特に中~上級者の間で評価が高まっている点は注目に値します。
性能や世代の違いに注目
CPUを選ぶうえで見逃せないのが「世代による性能の違い」です。単純にインテルかライゼンかという軸だけでなく、そのCPUがどの世代に属しているかによって、同じブランド内でも性能差が大きくなるため注意が必要です。
インテルは第12世代(Alder Lake)以降、**ハイブリッド構成(Pコア+Eコア)**を採用するようになり、従来のインテルCPUとはまったく異なる設計に進化しました。これにより、バックグラウンド処理や省電力管理が向上し、総合的な性能は大幅に改善されました。第13世代(Raptor Lake)ではキャッシュ構造やクロック性能がさらに向上し、ハイエンドモデルではゲーミング性能が他を圧倒しています。
一方、ライゼンはRyzen 3000シリーズから明確に進化し、Ryzen 5000シリーズでは**IPC(1クロックあたりの命令実行数)**が劇的に向上。これにより、従来はインテルが優位だったシングルスレッド性能でもライゼンが拮抗、あるいは上回る場面も出てきました。Ryzen 7000シリーズでは、AM5プラットフォームへの移行とともにDDR5メモリやPCIe 5.0に対応し、次世代の高速化環境に備えた設計がなされています。
▼世代ごとの比較表(主な傾向)
| メーカー | 世代名・型番 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| インテル | 第10世代(Comet Lake) | コスパ重視、ゲーム性能は良好だがやや旧式 |
| インテル | 第12世代(Alder Lake) | Pコア+Eコアのハイブリッド設計、処理効率が大幅向上 |
| インテル | 第13世代(Raptor Lake) | クロック性能向上、ゲーミング最強クラス |
| ライゼン | Ryzen 3000シリーズ | マルチスレッドに強く、コスパの高い構成が魅力 |
| ライゼン | Ryzen 5000シリーズ | IPC向上でゲーム・作業の両立が可能に |
| ライゼン | Ryzen 7000シリーズ | DDR5/PCIe5対応。今後の長期的なアップグレードにも対応可能 |
同じブランドのCPUであっても、世代が違えば性能も機能もまるで別物です。価格だけで判断せず、「どの世代のどのモデルか?」までしっかり確認することが、後悔しない選び方のコツです。
続けて他の見出しについてもご希望でしたらお伝えください。次に書いてほしい見出しはありますか?
価格とコスパを比較
CPU選びで最初に気になるのが「価格に見合った性能かどうか」、つまりコストパフォーマンスです。Core i7/i9やRyzen 7/9といった上位モデルは、どれも高性能ですが、得意分野が異なり、用途によって満足度も変わります。
下記の比較表では、価格帯と機能のバランスを中心にまとめています。
| CPUモデル名 | 価格帯(目安) | コア/スレッド | 特徴と向いている用途 |
|---|---|---|---|
| Core i7-13700K | 約6.5〜7万円 | 16/24 | ゲーム・編集・配信をバランスよくこなす万能型 |
| Core i9-13900K | 約8.5〜9.5万円 | 24/32 | あらゆる用途に高水準で対応、プロ用途にも◎ |
| Ryzen 7 7700X | 約5.5〜6.5万円 | 8/16 | ゲーム・一般作業向き、高いシングル性能 |
| Ryzen 9 7900X | 約7.5〜8.5万円 | 12/24 | 動画編集やマルチタスクに強い多機能モデル |
ゲーミング性能を重視しつつ、作業も快適にしたいならCore i7-13700Kがバランス良好。一方、価格に対するマルチコア性能を見れば、Ryzen 9 7900Xは編集や並列処理でコスパの高い選択です。
つまり、予算と使い道を明確にすると、どちらが“コスパの良い買い物”になるか判断しやすくなります。
ベンチマークで見る性能差
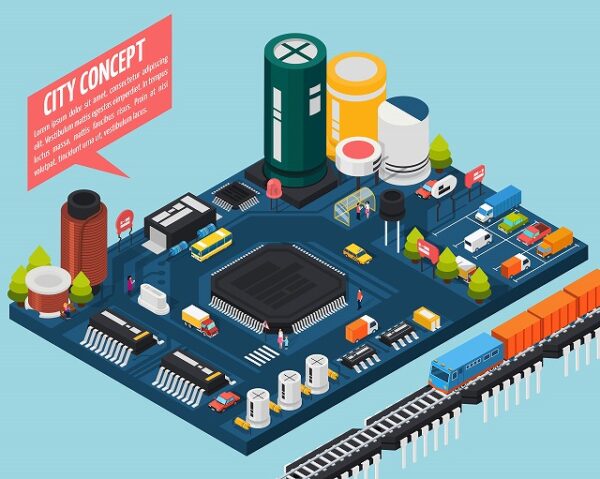
実際の処理性能を知るには、ベンチマークスコアが有力な参考になります。ここでは、**Cinebench R23(シングル・マルチ)**と、人気ゲームでのフレームレート比較を用いて、4つの上位CPUの性能差を見ていきましょう。
▼Cinebench R23 スコア比較
| モデル | シングルスレッド | マルチスレッド |
|---|---|---|
| Core i7-13700K | 約2,000 | 約30,000 |
| Core i9-13900K | 約2,100 | 約38,000 |
| Ryzen 7 7700X | 約1,950 | 約19,000 |
| Ryzen 9 7900X | 約1,980 | 約27,000 |
インテルはハイブリッド構成によりシングル・マルチ両方で強く、特にi9は総合最強クラス。ライゼンはマルチ性能でRyzen 9が強みを発揮。エンコードや並列作業に最適です。
▼ゲームベンチマーク例(フルHD設定)
| タイトル | Core i7-13700K | Core i9-13900K | Ryzen 7 7700X | Ryzen 9 7900X |
|---|---|---|---|---|
| Apex Legends | 約270 fps | 約285 fps | 約245 fps | 約255 fps |
| Valorant | 約400 fps | 約420 fps | 約370 fps | 約375 fps |
| Cyberpunk 2077 | 約135 fps | 約145 fps | 約130 fps | 約132 fps |
ゲーミング性能ではインテル勢が優勢。特にフレーム安定性と高リフレッシュレート対応に強みがあります。動画編集・配信重視ならRyzen 9のマルチスレッド性能が武器に。
総合的に見ると、
-
ゲーム中心なら「Core i7 / i9」が最適
-
動画制作・エンコード中心なら「Ryzen 9」が力を発揮します
どちらも高性能ですが、「何を重視するか」によって、選ぶべきモデルは明確になります。
CPU インテル(Intel)とライゼン(Ryzen)はどっちがおすすめ?
-
ゲーム用途に強いのはどっち?
-
配信に向いているのはインテルか?
-
動画編集に最適なCPUは?
-
インテルに多い不具合の事例
- ライゼンはやめとけと言われる理由は?
-
ライゼンで動かないソフト一覧とは?
-
インテルとライゼン以外の選択肢も検討
ゲーム用途に強いのはどっち?

PCでゲームを快適に楽しみたい場合、CPUの選び方がプレイ体験に大きく影響します。特にフレームレートや描画の滑らかさに関係する「シングルスレッド性能」や「キャッシュ容量」が重要なポイントになります。
ゲーム用途においては、インテル製CPUが有利とされるシーンが多いです。インテルは第12世代以降、Pコア(高性能コア)とEコア(省電力コア)を組み合わせたハイブリッド構成を採用しており、負荷の高いゲーム処理を効率的に行えます。また、クロック周波数も高いため、フレームレートが安定しやすく、特にeスポーツタイトル(例:Valorant、Apex Legends、CS2)ではパフォーマンスの差がはっきりと出ることがあります。
一方、ライゼンもRyzen 5000シリーズ以降では大きく進化し、多くのゲームで高いパフォーマンスを発揮しています。ただし、一部のゲームエンジンや古いタイトルでは、インテル向けに最適化されていることが多く、Ryzenだと若干不安定になるケースもあります。
▼代表的なゲームベンチマーク比較(平均フレームレート)
| ゲームタイトル | Intel Core i5-13600K | Ryzen 5 7600X |
|---|---|---|
| Apex Legends | 約265 fps | 約245 fps |
| Cyberpunk 2077 | 約135 fps | 約130 fps |
| Valorant | 約400 fps | 約370 fps |
こうしたベンチマーク結果を見ると、最新世代であればどちらも十分な性能がありますが、より高い安定性と平均フレームレートを求めるなら、インテルがやや優勢と言えます。特に144Hz以上のゲーミングモニターを使う人や、競技性の高いプレイヤーにはインテルが選ばれる傾向があります。
配信に向いているのはインテル?

ゲーム実況やライブ配信を行う場合、CPUに求められるのは「リアルタイムエンコード処理」と「安定した同時処理性能」です。OBSやXSplitなどの配信ソフトはCPUに高負荷をかけるため、配信中にゲームも同時に行う場合、CPU選びの影響は大きくなります。
インテルは第12世代以降、Quick Sync Videoという独自のハードウェアエンコード機能を搭載しています。これにより、配信時のエンコード処理をCPUではなく専用回路で処理できるため、ゲーム中のフレームレート低下を最小限に抑えることが可能です。特に配信初心者や設定に詳しくない人でも、安定した画質で配信できるのが魅力です。
一方、ライゼンはコア数が多いため、ソフトウェアエンコードで高画質な配信を行いたい中級〜上級者に向いています。Ryzen 9 7900Xなど、12コア以上のモデルを使えば、ゲーム・配信・録画のすべてを高品質で同時に処理することができます。ただし、Quick Syncのような専用エンコード支援がないため、設定やパフォーマンスチューニングが必要になります。
▼配信スタイル別のおすすめCPUタイプ
-
配信初心者/操作の簡単さ重視:インテル(Quick Sync対応)
-
高画質配信/マルチ配信(Twitch+YouTubeなど):ライゼン(高コア数モデル推奨)
-
OBSで録画+配信+編集を同時に行いたい:Ryzen 9やRyzen 7の上位モデル
最終的には、配信の目的やスタイルに合わせて選ぶのがポイント。インテルは「安定感と扱いやすさ」、ライゼンは「高性能と柔軟性」に優れていると考えると選びやすくなります。
動画編集に最適なCPUは?

動画編集では、素材の読み込み、タイムラインの操作、書き出し(エンコード)など多くの工程がCPUに依存します。そのため、コア数・スレッド数の多さ、キャッシュ構造、さらには対応するメモリ規格など、総合的な処理能力が求められます。
動画編集用途ではライゼンが特に高く評価されています。理由は、同価格帯でより多くのコアを持つモデルが多く、マルチスレッド処理に強いからです。たとえば、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveといったプロ向け編集ソフトは、複数のスレッドを活用してレンダリング処理を高速化できます。Ryzen 7 7700XやRyzen 9 7900Xのような8~12コアのモデルは、4K編集やカラーグレーディングにも対応できる実力を持っています。
ただし、インテルの上位モデルも無視できません。たとえば、Core i7-13700Kは8つのPコアと8つのEコアで合計24スレッドと、ハイブリッド構成でバランスの良い性能を発揮します。また、Quick Syncによる高速エンコードも使えるため、作業時間の短縮やファイルのプレビューも快適です。
▼動画編集向けおすすめCPUモデル比較
| 用途 | おすすめCPU(インテル) | おすすめCPU(ライゼン) |
|---|---|---|
| フルHD編集(趣味レベル) | Core i5-13400F | Ryzen 5 5600X |
| 4K動画編集・エフェクト多用 | Core i7-13700K | Ryzen 9 7900X |
| 同時に配信や録画も行いたい場合 | Core i9-13900K | Ryzen 9 7950X |
つまり、本格的な編集作業や高解像度動画に対応したいならライゼン上位モデル、手軽さや作業の安定感を重視するならインテルも選択肢に入るというバランスです。編集スタイルやソフトとの相性を考慮して選ぶことで、より快適な動画制作環境が整います。
インテルに多い不具合の事例
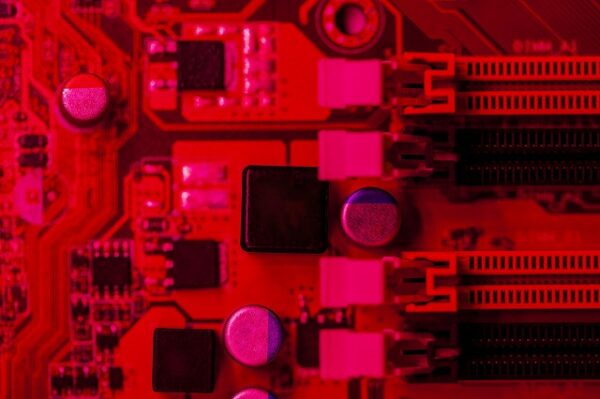
インテル製CPUはパフォーマンスや安定性で高く評価される一方で、過去にはいくつかの不具合や仕様上の課題が報告されています。これらは特定の世代や使用環境に依存することが多いため、事前に傾向を知っておくと安心です。
とくに目立ったのが、第12世代・第13世代の高性能モデルにおける高温化と電力過多問題です。これらのCPUはPコアとEコアを組み合わせたハイブリッド構成を持つ一方、発熱が大きく、冷却性能が十分でない環境では性能が安定しないことがあります。
また、以下のような不具合報告も見られます:
-
BIOSとの相性による起動不良(とくに最新世代発売直後に多い)
-
Windows 11との互換性警告(TPM 2.0の設定未対応など)
-
省電力モードでのクロック固定や挙動不安定
-
特定のゲーム・アプリケーションでのクラッシュやブルースクリーン(例:FortniteでのDirectX関連エラー)
さらに、最新世代でのOC(オーバークロック)設定が複雑化しており、初心者が安易に扱うと故障リスクが高まるという側面も指摘されています。
もちろん、これらの不具合の多くはマザーボードのアップデートや電源・冷却環境の見直しで対処可能です。ただし、インテル製CPUを選ぶ場合は、対応パーツとの相性や冷却性能を重視した構成にすることが、快適な動作のカギとなります。
ライゼンはやめとけと言われる理由は?
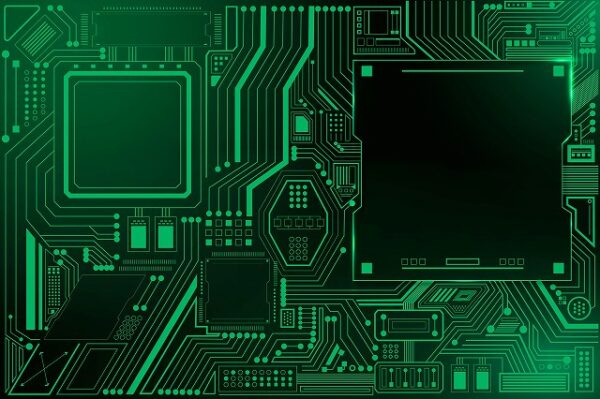
Ryzen(ライゼン)は高性能なCPUとして評価されていますが、一部のユーザーやネット掲示板などで「やめとけ」と言われる場面もあります。これは製品自体の問題というより、特定の使い方やユーザー層にとって「扱いづらい」と感じられるポイントがあるためです。以下に、その主な理由を整理して説明します。
1. 初心者にとって自作難易度がやや高い
Ryzen搭載のPCを自作する場合、マザーボードのBIOS設定やメモリの相性確認など、インテルに比べてやや細かい調整が必要になることがあります。特にAM5環境では、DDR5メモリの設定や最適化が初心者には難しく感じられることもあります。
2. 一部ソフトやゲームとの相性
古いアプリケーションやDirectX 9以前のゲームなど、インテルを前提に開発されたソフトではRyzen環境でうまく動作しない、もしくは不安定になるケースがあります。特に業務ソフトやカスタムツールでは、Ryzenでの動作確認がされていないことも多いため注意が必要です。
3. 初期不具合やBIOS対応の遅さ
新世代Ryzenがリリースされた直後は、マザーボード側のBIOSアップデートが追いつかず、正常に起動しない・安定動作しないなどのトラブルが報告されることがあります。パーツ構成によっては、初回起動時に別のCPUでの仮起動が必要になるケースもあり、「やめとけ」と言われる原因になります。
4. 内蔵グラフィックス非搭載モデルが多い
Ryzenシリーズは「G」がついたモデル以外、基本的に内蔵GPUを搭載していません。そのため、別途グラフィックボードを用意しないと画面表示すらできない場合があり、ライトユーザーや予算を抑えたい人には不向きと感じられがちです。
5. 情報が断片的で正確な選び方が難しい
Ryzenは世代ごとの進化が大きいため、旧世代の情報が混在していたり、ネット上で誤った評価が拡散されていたりすることがあります。適切なモデルを選ばないと、「思っていたほどの性能が出なかった」といった不満につながる可能性もあります。
このように、「ライゼンはやめとけ」という声は主に初心者や特定用途のユーザーにとってのハードルが原因であり、製品の性能そのものを否定するものではありません。正しい知識と準備をもって使えば、ライゼンは非常にコストパフォーマンスの高い選択肢です。
ライゼンで動かないソフト一覧とは?
Ryzenシリーズは高いマルチスレッド性能を誇る一方、一部の古いアプリケーションや特殊な業務ソフトとの相性問題が報告されています。これは、ソフトウェア側がインテル向けに最適化されているケースがあるためです。
実際に報告されている「Ryzenで動かない、または不安定になるソフト」の一例は以下の通りです:
-
一部のCAD系業務ソフト(例:古いバージョンのAutoCADやSolidWorks)
-
BIOSレベルでのハードウェア制御ツール(特定メーカー製のファームウェア管理ツールなど)
-
古いゲームタイトル(DirectX 9以前)
→ 例:『The Sims 2』『RollerCoaster Tycoon 3』など、Ryzen環境でクラッシュするケースあり -
古い会計・業務ソフト
→ 一部中小企業向けの業務ソフトではRyzen環境下で動作確認されていないケースも
これらの問題の多くは、最新パッチやアップデート、仮想環境の利用で回避可能ですが、長年使っている業務用ソフトがある場合は、メーカー公式の対応情報を事前に確認するのが確実です。
なお、Ryzen 5000シリーズ以降ではアーキテクチャの安定性が向上し、動作報告されるソフトも増えています。とはいえ、インテルが依然として業務用途の「標準環境」として採用されやすい点は変わっていません。
インテルとライゼン以外の選択肢も検討
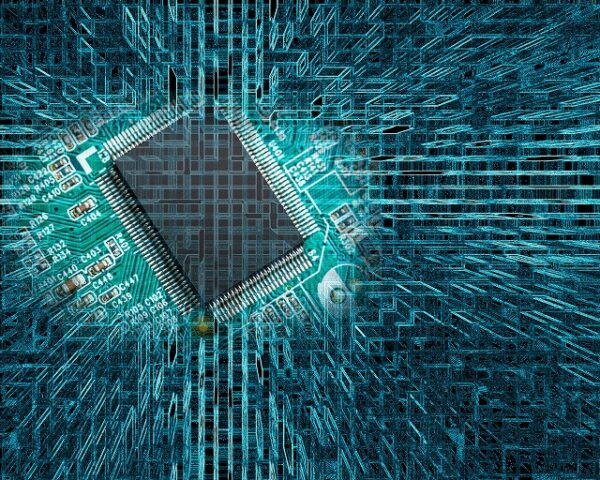
CPU市場では「インテル vs AMD(ライゼン)」の2強が中心ですが、それ以外の選択肢も一部で注目されています。特に次のような用途や条件では、他メーカーや特定用途向けのCPUが合理的な選択肢となることがあります。
1. Apple Mシリーズ(Macユーザー向け)
Appleの独自設計であるM1・M2・M3チップは、動画編集・音楽制作・写真加工といったクリエイティブ用途で非常に高い評価を受けています。高効率かつ低発熱で、Final Cut ProやLogic ProなどApple純正ソフトとの相性も抜群です。
2. ARM系CPU(開発・組み込み向け)
最近では、省電力性に優れるARM系CPUもPC分野に進出し始めています。Chromebookや一部のWindows on ARMデバイスに採用され、Web閲覧や事務用途での軽快な動作が可能です。ただし、互換性の問題があるため特殊用途向けと考えるのが現実的です。
3. ハイエンド向け:Intel Xeon / AMD Threadripper
サーバーやプロ向けワークステーションでは、インテルXeonやAMD Threadripperが定番です。これらは数十コアを搭載し、科学計算・3Dレンダリング・大型映像編集といった用途に適しています。ただし、価格も高額で、一般ユーザーにはオーバースペックな場合が多いです。
▼ インテル・ライゼン以外のCPUまとめ表
| CPUブランド | 主な特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| Apple Mシリーズ | 高効率・低発熱・ソフト最適化 | Macでのクリエイティブ作業 |
| ARM系(Snapdragonなど) | 超低消費電力、軽作業向き | 開発用、モバイルノートPC |
| Xeon / Threadripper | 業務用ハイエンド、多コア構成 | サーバー、映像制作、大規模演算 |
日常使いやゲーミングにはインテル・ライゼンが引き続きベストですが、用途によっては他の選択肢もコスト効率や相性で有利になることがあります。選択肢を広げて考えることが、失敗しないPC選びにつながります。
CPU インテル ライゼンの違いと選び方を総まとめ
-
インテルはシングルコア性能が高くゲーミングに向いている
-
ライゼンはマルチコア性能に優れ動画編集や配信に強い
-
インテルはハイブリッド構成でPコアとEコアを使い分ける
-
ライゼンはすべてのコアが同一構成で処理の安定性がある
-
世代ごとにソケット変更が多いのはインテルの特徴
-
長期的な互換性を持つAM4/AM5ソケットはライゼンに多い
-
インテルはQuick Syncを搭載し配信やエンコードに強い
-
ライゼンはG付き以外に内蔵GPUがなくグラボが必須
-
初心者にはBIOS設定やパーツ選定が簡単なインテルが扱いやすい
-
自作やパフォーマンス重視のユーザーにはライゼンが好まれる
-
一部旧ソフトやCADツールはライゼン環境で動作が不安定な場合がある
-
ゲームベンチマークではインテルの方が高フレームレートを記録することが多い
-
コスパ重視ならRyzen 9のような多コアモデルが優位な場面がある
-
インテルの高性能モデルでは発熱や電力過多の課題もある
-
インテルとライゼン以外にApple MシリーズやXeonも選択肢となる